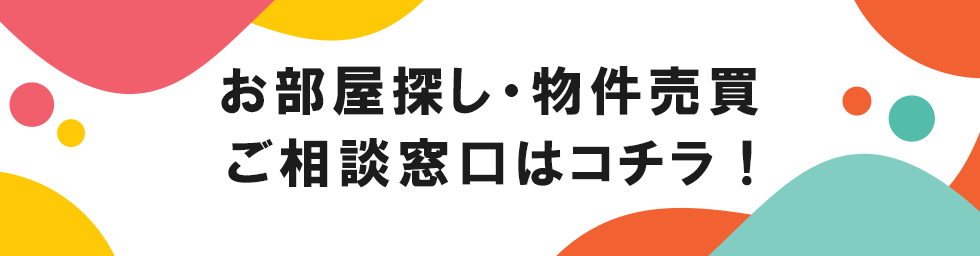資産運用
資産運用
「根抵当権」ってなに!?メリットの裏に潜む注意点を説明します!

「根抵当権」ってなに!?メリットの裏に潜む注意点を説明します!
不動産投資で金融機関から融資を受ける際、多くの場合、購入する収益物件や、すでに所有している別の物件に「抵当権」を設定するのが一般的です。
この抵当権は、万一返済が滞った場合、金融機関がその不動産を売却して融資金を回収できるようにする、いわば“担保のための権利”。不動産投資家にとってはおなじみの制度です。
ところが、ときどき銀行などから「根抵当権で設定させてほしい」と持ちかけられることがあります。聞き慣れない用語に戸惑うかもしれませんが、何となく「手続きが簡単になる」「追加融資が受けやすくなる」といったイメージを持つ方も多いようです。
しかし実際には、根抵当権には投資家として注意すべき点や、場合によっては不利になりかねないデメリットもあります。
本稿では、抵当権と根抵当権の違いを整理しつつ、投資家としてどのように判断すべきかを分かりやすくご説明します。
■抵当権とは?基本事項をおさらいします!
まずは、投資家にとってなじみ深い「抵当権」について、あらためて簡単に整理しておきましょう。
抵当権とは、借入金の担保として、不動産に設定される権利のこと。
融資を受ける際には、金融機関が貸付先の不動産にこの抵当権を登記することで、万が一の債務不履行時に優先的に回収できる権利を確保することになります。(不動産投資の実務では、新規購入する収益物件だけでなく、既に所有している他の収益物件を「共同担保」として差し出すこともあります)
投資家側からすれば、融資のたびに返済計画や収支、物件価値などの審査を受ける必要があり、確かに手間はかかりますが、そのぶん案件ごとに金融機関を選べるという柔軟さがあり、担保余力が回復すれば別の銀行からの借入も可能になるというメリットがあります。
次々に収益物件を買い増していく投資家にとって、こうした“物件ごとの資金調達の自由度”は、意外と重要なポイントとなります。
■根抵当権とは?メリットと見落とされがちなリスク
では、本題の根抵当権のご説明に入りましょう。
根抵当権とは、特定の債権(たとえば○年○月○日の融資契約)に対してではなく、「一定の範囲内で繰り返し発生する融資」などを一括して担保に取る制度です。
ひとことで言えば、“いちいち担保設定をやり直さなくても、同じ不動産を使って何度でも借りられる仕組み”ということになります。
たとえば、物件を担保に500万円までの極度額を設定しておけば、その範囲内で300万円借りて返済し、また200万円借り直す・・・といった運用が可能になります。事務手続きや審査が簡略化されるぶん、リフォームローンなどの小口融資を繰り返し利用したい人には便利な制度です。
しかし、不動産投資で利用するには、以下のような注意点も存在します。
1つ目は、「完済しても担保が自動では外れない」「担保物件の活用や売却がしにくくなる」リスクです。
通常の抵当権であれば、借入を完済すれば担保権の抹消が可能です。しかし根抵当権では、将来また借り入れる前提になっているため、完済後も担保が残り続け、抹消には金融機関の同意が必要となります。
加えて、根抵当権が複数物件に設定されている(共同担保)場合は、その一部だけを売却したくても、銀行から「担保力が落ちる」と判断され、解除に応じてもらえない可能性があることにも注意が必要です。
2つ目は、他行からの融資を受けにくくなるリスクです。
根抵当権では、登記簿上に「極度額(たとえば1000万円)」は記載されますが、実際にいくら借りているかは外からは分かりません。他の金融機関にとっては「いくら担保に余力が残っているのか」が不透明なため、「この物件は担保として使えない」と判断される可能性が生じてしまいます。
3つ目は、「本当に期待したいときには役に立たない可能性が高い」ことです。
根抵当権が設定されているとはいえ、新たに大きな金額を借りようとすれば極度額の範囲を超えることが多いもの。
一番投資家が期待したい新規の収益物件購入時や大規模修繕などのシーンでは、結局は新たな融資審査や担保評価を受ける可能性が高く、結果的に根抵当権のリスクだけを抱え込み、「肝心なときには普通の抵当権とあまり変わらなかった」と期待が空振りになることもあるでしょう。
■根抵当権は、投資戦略に応じて、慎重に選ぶべき!
このように、根抵当権は便利な面もある一方で、少なくとも「誰にでも向く制度」ではありません。
とくに、複数の金融機関と取引をしながら物件を増やしていきたい方や、借り換えや売却によって機動的に資産拡大を狙うような方にとっては、やはり通常の「抵当権」で進めた方が無難な場合が多いでしょう。
一方で、「すでに主力銀行と深い関係を築いており、今後もその銀行からしか借りない」という戦略であれば、根抵当権の設定によってスムーズな借入が可能になり、コスト面や手続き面でも恩恵があるかもしれません。
いかがでしょうか。
このように「抵当権」と「根抵当権」は似て非なるものです。
特に不動産投資においては、その違いが今後の融資戦略・資産拡大計画そのものに直結する可能性があるものとして、十分に慎重な判断をするべきでしょう。