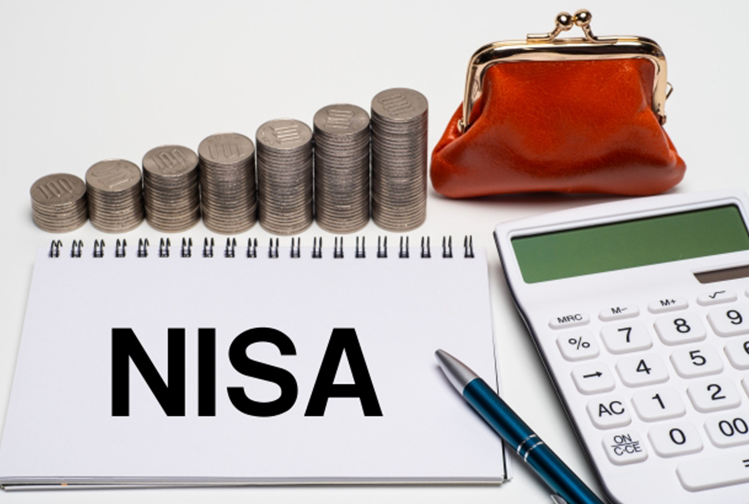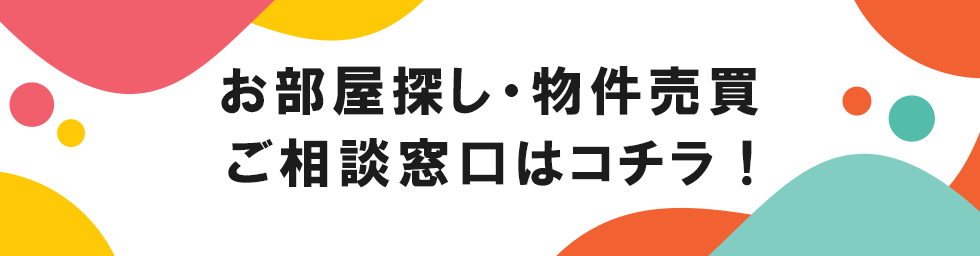資産運用
資産運用
賃上げが進まない本当の理由――内部留保の誤解と“両方取り”の限界

近年、政府や労働組合、さらには一般消費者からも「なぜ日本企業はもっと賃上げをしないのか」という声が繰り返しあがっています。実質賃金はこの30年ほとんど横ばいで、OECD諸国と比べても日本の給与水準は見劣りする状況です。
政治の場でも「賃上げ促進」が掛け声のように繰り返され、メディアでも企業の賃上げ動向が大きく報じられるようになりました。とりわけ、企業が抱える「内部留保」の規模が拡大していることが強調されると、「これだけ余裕があるなら社員に回せばよいではないか」という批判が強まります。
しかし、現実はそれほど単純ではありません。内部留保の実態は誤解されがちであり、また日本独自の雇用慣習が、企業が慎重な姿勢を崩さない大きな背景となっています。
本稿では、なぜ日本で賃上げが進みにくいのか、その構造的な要因を整理してみたいと思います。
■内部留保は“現金の山”ではない
まず、よく批判の対象となる「内部留保」について確認しておきましょう。内部留保とは会計上「利益剰余金」と呼ばれるもので、企業がこれまで稼いだ利益のうち配当や役員賞与に回さなかった分が積み上がったものです。
たしかに、企業の内部留保が年々順調に積み上がっている事実は疑いがありません。財務省の法人企業統計などの調査結果から、その推移を容易に確認することができます。
---------------------------------------------------------
<参考>
財務省ホームページ『法人企業統計調査』
https://www.mof.go.jp/pri/reference/ssc/index.htm?utm_source=chatgpt.com
---------------------------------------------------------
ところが、この事実を以って、「企業が巨額の現金をため込んでいる」と解釈するのは早計です。内部留保の多くは設備投資や研究開発、在庫や有価証券など、さまざまな形で運用されており、現金預金は全体の一部でしかないためです。
もちろん企業によっては手元資金を厚めに確保している場合もありますが、それは経営者にとって事業継続性を守るための重要な備えです。金融機関からの融資や企業格付けにおいても、バランスシートの健全性は重視されます。いざ景気が悪化したとき、手元資金が不足すれば事業そのものが立ち行かなくなります。
したがって「内部留保を取り崩して賃上げに回せ」という主張は、一見もっともらしく聞こえますが、現実には企業経営の基本を無視した危うい発想でもあるのです。
■雇用慣習が生む“賃上げの重さ”
次に、日本特有の雇用慣習に目を向けてみましょう。
欧米の企業であれば、景気が好調なときには賃上げや高額なボーナスで従業員に報い、不況になれば人員削減や賃下げによって調整するのが一般的です。極端にいえば、
① 業績が良ければしっかり賃上げするが、悪化すれば解雇や賃下げも辞さない
というスタイルです。
一方、日本の企業文化は大きく異なります。戦後長らく続いてきた「終身雇用」や「年功序列」の慣習が象徴するように、解雇は極めて限定的にしか認められず、賃下げも容易ではありません。厚労省の労働契約に関する調査でも、日本はOECDの中でも解雇規制が強い国の一つと位置づけられています。その代わりに企業は、業績が良くてもベースの給与水準は大きく引き上げず、賞与や一時金によって限定的に還元するという手法をとってきました。
つまり、
② 賃上げは控えめにしつつ、解雇や賃下げは極力回避する
というスタイルです。
この両者を比べてみれば明らかですが、従業員から「好調なときは賃上げしてほしい、でも不況期には雇用も給与も守ってほしい」と望むのは、いわば“両方取り”です。
残念ながら、そんなに都合のよい制度設計は存在しません。企業が賃上げに慎重になる背景には、この日本ならではの雇用安定モデルがあるのです。
■経営者が考える「事業継続性」という視点
さらに忘れてはならないのは、経営者が常に「事業を持続させる」責任を負っているという点です。従業員にとっては目の前の給与が最も関心のある問題でしょうが、経営者の立場から見れば、5年後、10年後に会社が存続できているかどうかが死活問題です。
企業が融資を受ける際、銀行は必ず財務バランスや自己資本比率をチェックします。内部留保を単純に吐き出してしまえば、一時的に従業員は喜ぶかもしれませんが、金融機関からの信用を失い、将来の投資や雇用維持に支障が出かねません。実際、経団連や中小企業庁の調査でも「一過性ではなく持続的な賃上げを実現する必要がある」と繰り返し述べられています。
経営者が賃上げに慎重な姿勢を見せるのは、単に「けち」だからではなく、こうした財務健全性と事業継続性を重視しているからにほかなりません。短期的な利益分配と長期的な生存戦略の狭間での判断であることを理解する必要があります。
いかがでしょうか。
賃上げが進まない理由を「企業の内部留保のせい」と一言で片づけるのは容易ですが、その背後にはいくつもの事情があります。内部留保は現金の山ではなく、事業継続のために必要な投資や安全網でもある。加えて、日本独自の雇用慣習は「好況時に賃上げ、不況時に解雇」という柔軟なモデルを許さず、賞与や一時金での調整を主軸にしてきました。
結局のところ、社会がどの労働契約モデルを望むのかという選択が問われています。①賃上げと解雇のセットを受け入れるのか、②賃上げは控えめでも雇用を守るのか。それとも、非現実的な“両方取り”を求め続けるのか。
賃上げの停滞は経営者の怠慢ではなく、日本経済と雇用制度が抱える構造的な課題です。健全な議論のためには、内部留保や雇用慣習の実態を正しく理解し、冷静に向き合う必要があるのではないでしょうか。