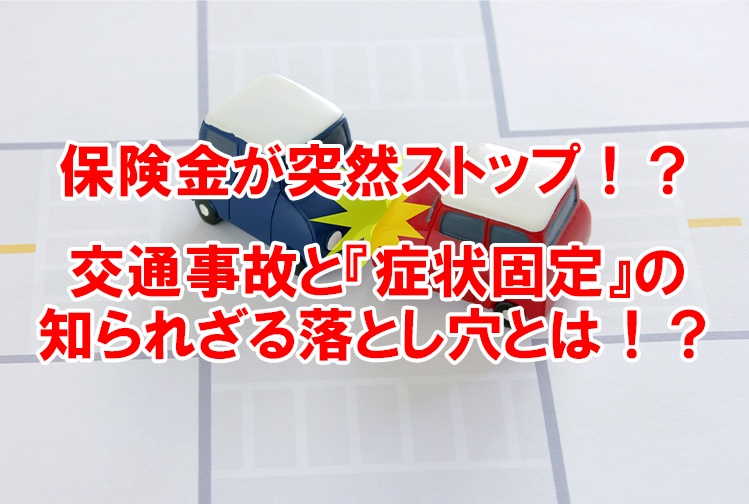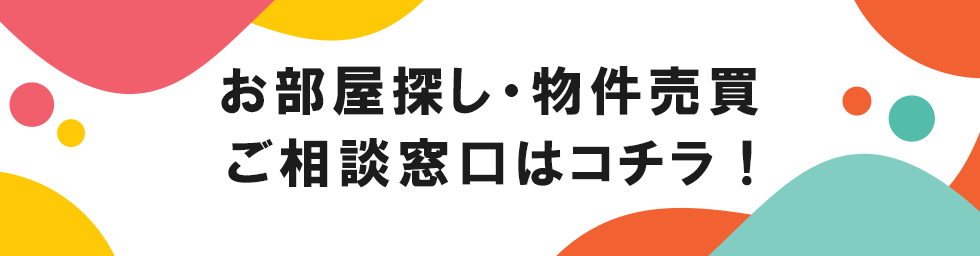保険年金
保険年金
「GLTD」とは何?メリット・デメリットを解説

企業の福利厚生制度のひとつとして知られる、GLTDをご存じでしょうか。
GLTDとは、団体長期障害所得補償保険のことを指し、従業員が就業不能状態に陥った際に所得を一定程度補償してくれるといった特徴があります。
そこで今回はGLTDのメリットやデメリットについて、わかりやすくまとめてみました。
GLTDに興味のある方はメリット・デメリットをしっかりと把握した上で検討してみてください。
■GLTDとは?(団体長期障害所得補償保険)とは

GLTDとは損害保険の一種で、病気やケガで就業不能となった従業員に対し、長期間の収入源を保証するものです。
一般的には、有給制度や健康保険だけでは補えない所得の損失を最長で定年年齢まで補償するケースが多く見受けられます。
長期にわたって収入減をカバーしてもらえるため、安心して療養に専念できるほか、残された家族も生活に困らずに済むでしょう。
[PR] 自信を持って保険の決断をする - 保険見直しはプロにお任せ!
▼就業不能状態とは
GLTDで保険金が支払われるのは、以下のような就業不能状態となった場合に限られます。
-
・入院中である(精神疾患によるものを除く)
-
・在宅療養をしている(精神疾患によるものを除く)
-
・障害等級1級または2級に認定されている
-
・その他就労が困難であると認められる状態にある
とはいえ、GLTDの補償内容は保険会社や付帯する特約によって異なります。
加入検討時は複数の保険会社を比較検討した上で、利用するかどうかの判断を下すことが大切です。
▼保険金が支払われる期間
GLTDの保険金が支払われる期間は、以下のいずれかまでです。
-
・就業不能状態が終了したとき
-
・支払い対象期間が終了したとき(60歳あるいは65歳となります)
また、就業障害が長引いて会社を退職した場合であっても、保険金の支払い条件を満たしてさえいれば対象期間内は保険金を受け取れます。
▼従業員の自己負担で補償上乗せも可能
GLTDは、保証料全額を会社が負担するだけではありません。
従業員が希望すれば任意で補償の買い増しもできるため、ニーズに合った補償割合に調整可能です。
■GLTDの歴史
GLTDの原型は、20世紀初めのアメリカの労働者による共済制度といわれています。
1929年に起こった世界大恐慌以来、アメリカでは所得補償制度としてすごいスピードで普及しました。
いまもなお普及率は高く、社員数501人〜2000人規模の企業の内、約95%が導入済みといわれています。
また、そのうち70%は全員加入型あるいは全員加入型+任意加入型というところからも、関心の高さがうかがい知れるでしょう。
一方の日本では1994年、当時の大蔵省の認可を得て企業への導入が始まりました。
従業員へのリスクマネジメントができる便利な保険商品として、現在でも普及が進んでいます。
■従業員がGLTDに加入するメリット

ここでは、従業員がGLTDに加入するメリットについて見ていきましょう。
▼最長で定年まで月々の給与の一部が補償される
日本の健康保険制度では、従業員が業務外の事由による病気や怪我で休業した場合、最長で1年6ヶ月の間は給与の約2/3の金額を傷病手当として受け取ることができます。
また、その1年6ヶ月以降も働けない状態であれば、所定の要件を満たすことで障害年金の受け取りが可能です。
しかし、障害厚生年金3級の最低支給額が年間584,500円とされており、これだけで生計を維持するのは難しいでしょう。
対するGLTDでは、加入しておくことで上述した公的補償にプラスして毎月保険金を受け取れます。
万が一、長い期間働けなくなった場合でも、GLTDに加入しておくことで本人や家族の生活の不安が軽くなりますよね。
なお、業務に一部復職した場合であっても就業に支障があることが原因で、20%超の所得損失がある場合には所得損失率に応じた保険金が支払われるので安心です。
[PR] 信頼できる保険で、あなたの長期的な安心を保証します
▼民間の就業不能保険より保険金が受け取りやすい
GLTDと民間の就業不能保険には、基本的に大きな違いはありません。
ただ、民間の就業不能保険は現状の仕事どころか、事務などの軽い仕事さえできない状態でなければ就業不能と認められないといった厳しい条件が設定されているケースがほとんどです。
GLTDであれば、復職できない状況であれば比較的容易に給付要件を満たせます。
そのため、保険金の受け取りやすさといった面では民間の保険よりもメリットがあるでしょう。
▼休職していてもサポートが手厚い
がんなどで休職した場合であっても、早期サポートを受けられるメリットもあります。
また、加入先のGLTDによっては精神疾患による就業不能であってもサポートを受けられるほか、専門家による復職支援も受けられることも。
そのため、新しいキャリアを描いている場合であっても、金銭的・精神的な安心感が得られるといえます。
■企業がGLTDを導入するメリット
従業員がGLTDに加入するメリットについて理解したところで、企業側のメリットについても見ていきましょう。
▼就労不能になった従業員に長期補償を提供できる
GLTDを導入していることで、従業員に対し「安心して働ける場を提供している」といった企業の姿勢をアピールできます。
また、万が一就労不能になってしまったとしても、GLTDがあれば金銭面で大きな負担を抱くことなく安心して療養できるでしょう。
▼保険料の負担が少ない
団体保険であるGLTDは、団体割引が適用されるため民間の就業不能保険と比べると、保険料の負担が安くなります。
それぞれの保険内容に異なる点も多いため、比較は難しくなりますが、金額だけ比べるとGLTDは民間の約1/10くらいの保険料の負担となっています。
そのため、極めてコストパフォーマンスの高い保険だといえるでしょう。
▼色々なサービスが無料
GLTDを導入すると、福利厚生に役立つサービスを無料で利用可能です。
例としては、以下のようなサービスが用意されています。
-
・医療専門スタッフによる電話相談
-
・メンタルサポート
-
・法律やファイナンシャルサポートなど
こうしたサービスを実際に受けようと思うと一定の金額が必要となるため、無料で受けられるのは魅力的ですよね。
■GLTDのデメリット
GLTDにはメリットがある一方で、いくつかのデメリット(注意点)があります。
ここでデメリット(注意点)について、見ていきましょう。
▼所得補償保険の免責期間は補償対象外となる
GLTDには免責期間があります。
免責期間とは、傷病などで働けなくなってから保険金の支払いが始まるまでの期間のことです。
この期間は保険会社によって異なりますが、一般的には30日から1065日程度で設定できるケースがほとんどでしょう。
免責期間は短いほど保険料が高くなり、逆に長ければ保険料が安くなるといった特徴があります。
とはいえ、保険料を安くしたいがために免責期間を長くしてしまうと、収入は減少する一方なのに保険料が振り込まれないといった事態を招く恐れも。
保険金が支払われない期間が長ければ長いほど、本来の目的である福利厚生の充実を目指すことは難しくなってしまうのはデメリットといえます。
▼商品選びが難しい
GLTDは保険会社によって補償範囲や待機期間の設定が異なるため、加入検討時は複数の商品を比較する必要があるのもデメリットといえるでしょう。
また、GLTDは就業不能状態になり一定の待機期間が経過した後に補償が開始される独特の形態をとっています。
そのため、補償の規定が細かく決まっており、きちんと理解しておかないと認識のズレを引き起こしかねません。
加入する前に一度、保険や金融知識に長けたプロに相談することをおすすめします。
以上がGLTDに関するデメリット(注意点)になります。
■GLTDのメリット・デメリットを知っておきましょう
今回の記事では、GLTDのメリットとデメリットについてお伝えしました。
GLTDを導入することで、企業は民間の保険より安い保険料で従業員の生活を守れます。
また、従業員も安心して働けるだけでなく、モチベーションアップにも繋がるでしょう。
まさにwin-winの関係を築くことのできるGLTD。
メリット・デメリットを把握した上で興味がある方は是非この機会に検討されてみてはいかがでしょうか。
なお、レアルエージェンシーでは、個々に応じた資産形成や資産運用、節税対策の方法をお伝えするマネーセミナーを実施しています。
当社ライフコンサルタントがご要望や状況に合わせたオーダーメイドプランを作成し、独自のライフシミュレーションを活用して丁寧にご案内致します。
対面、オンラインのいずれでも対応可能ですので、ぜひこの機会にご検討ください。