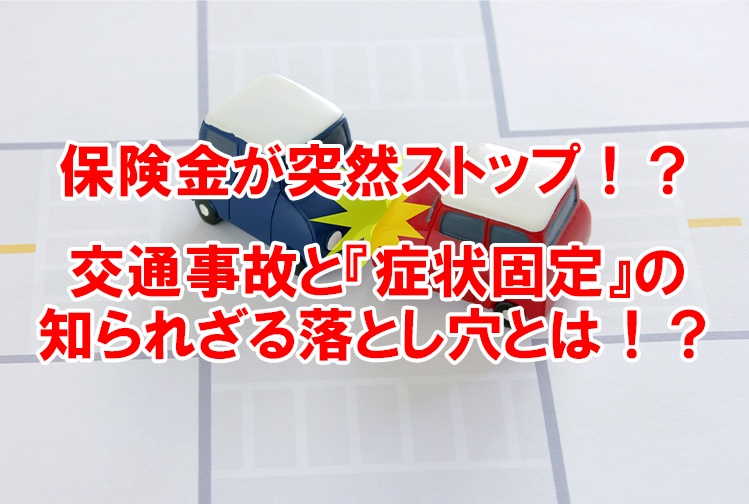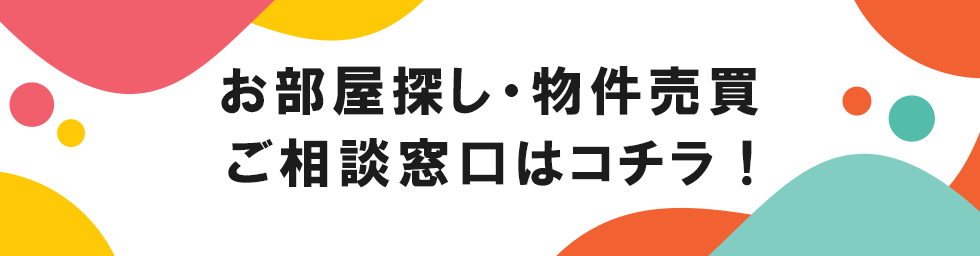保険年金
保険年金
新年度に考えたい!年金の「繰り上げ」「繰り下げ」を分かりやすく解説します!

新年度を迎え、職場の人間関係もリフレッシュした方も多いのではないでしょうか。
キリの良いこの時期に会社を退職する方もいることでしょう。
退職といえば、年金。
そして年金の話題で気になる点といえば、「いつからもらうのが得なのだろう?」ということではないでしょうか。
日本の公的年金制度は、制度改正(受給側からするとほぼ改悪ばかり)を繰り返し、2025年現在では65歳からの受給を原則とし、最も早くて60歳から年金を受け取れる「繰り上げ受給」、最も遅くて75歳まで繰り下げる「繰り下げ受給」が選べる設計になっています。
当然、早く年金を受給開始すれば1ヵ月あたり受給額は下がり、逆に年金受給を遅くすれば同、受給額は上がるわけですが、実際にどちらを選べば、どのくらい変わるのかまでは理解できておらず、漠然とした不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
公的年金制度は、老後の生活設計における重要な柱のひとつです。
制度の仕組みやメリット・デメリットを理解しないまま受給時期を決めてしまうと、将来的に「こんなはずじゃなかった…」と後悔することになりかねません。
そこで本稿では、公的年金の繰り上げ・繰り下げ受給について、「特に注意すべき2つのポイント」に絞ってわかりやすくご紹介していきます。
選択次第で、受け取れる総額や老後の安心感に大きな差が生まれることもあるため、自分にとって最適なタイミングを見極める参考にしていただければと思います。
■繰り上げ受給の落とし穴? 早くもらえるのは魅力だけど…
まずは、「繰り上げ受給」からご説明しましょう。
この制度では、原則65歳とされる年金受給開始年齢を、60~64歳の間で早めることができます。
「もう会社も辞めたし、年金を早くもらって生活の足しにしたい!」という方には、非常に魅力的に見える制度です。
しかし、ここで注意したいのが「減額率」です。繰り上げた場合、1ヵ月あたり0.4%(※)ずつ減額され、その減額は一生続きます。
(※)従来1ヵ月あたりの減額率は0.5%でしたが、2022年4月の法改正により、誕生日が昭和37年4月2日以降の方は減額率が0.4%となりました。

【出典】日本年金機構ホームページ『年金の繰上げ受給』より
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-01.html
例えば、60歳から5年間繰り上げた場合の減額率は24%、もとの年金受給額が月10万円であれば、月7万6,000円程度に減額される計算です。
また、「繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わらないこと」「原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求をする必要があること」といった点も覚えておくとよいでしょう。
[PR]ファイナンシャルプランナーが個別にご説明『NISAのはじめかた』
■繰り下げ受給は本当に“得”? 長寿リスクとどう向き合うか
もう一方の「繰り下げ受給」の制度では、原則65歳とされる年金受給開始年齢を、66~75歳(※)の間で遅くすることで、1ヵ月あたりの受給額を増やすことができます。
(※)従来繰り下げる年齢は70歳まででしたが、2022年4月の法改正により、誕生日が昭和27年4月2日以降の方は75歳まで繰り下げ請求ができることになりました。
繰り下げによる増額率は、1ヵ月あたり0.7%で、その増額は一生続きます。

【出典】日本年金機構ホームページ『年金の繰下げ受給』より
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-02.html
例えば、70歳まで繰り下げた場合の増額率は42%、もとの年金受給額が月10万円であれば、月14万2,000円に増額される計算です。
また、「繰下げ受給の請求をした時点に応じて年金が増額され、その増額率は一生変わらないこと」「老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に同時に繰下げ請求できること(この点、繰り上げ受給の申請と異なる!)」も押さえておきましょう。
■単純比較では「繰り上げ受給」または「65歳からの受給」が有利!?
では、「①繰り上げ受給を最大限(60歳)」「②何もしない(65歳)」「③繰り下げ受給を最大限(75歳)」の3パターンについて、何歳時点で、総額いくらの年金を受給できるのかを簡易的にシミュレーションしてみましょう。
------------------------------------------------------
【試算前提】 ※端数は四捨五入
①60歳まで繰り上げ受給(▲24%減額):⇒月額約7.6万円(年間約91万円)
②65歳より受給開始:月額10万円(年間120万円)
③75歳まで繰り下げ受給(+84%増額):月額約18.4万円(年間約221万円)
<75歳時点までの累計受取額>
①約1,365万円(91万円 × 15年)
②約1,200万円(120万円 × 10年)
③0円(まだ受給開始していない)
<80歳時点までの累計受取額>
①約1,820万円(91万円 × 20年)
②約1,800万円(120万円 × 15年)
③約1,105万円(221万円 × 5年)
<85歳時点までの累計受取額>
①約2,275万円(91万円 × 25年)
②約2,400万円(120万円 × 20年)
③約2,210万円(221万円 × 10年)
------------------------------------------------------
あくまで特定条件下における簡易的なシミュレーションですが、日本人の平均寿命とされる80歳前後で考えれば、単純な総受給額では「繰り上げ受給」または「65歳からの受給」が有利な可能性が高いということになります。
■総受給額の大小だけでは測れない現実もある!
しかし、個々人の年金受給開始時期を決めるにあたっては、単純な総受給額の大小だけで決めるのは危険です。
健康状態や健康寿命、年金以外の資産有無などによって、最適解は様々に分岐するからです。
また、年金は雑所得として扱われるため、繰り上げ受給をすることで税金・社会保険料の支払いが増える可能性、あるいは繰り上げ受給をして働きながら年金を受給することで、税金・社会保険料の支払いが増える可能性もあります。(特に、これら負担は65歳未満の年金受給者に大きくなる制度設計となっています)
纏めると、総受給額の大小に加えて、以下のような観点も判断材料に加えるべきでしょう。
<年金受給時点の判断材料>
・健康状態と平均寿命への見通し
・退職後の生活費や資産状況
・他の収入源(企業年金、退職金、貯蓄など)の有無
・扶養家族の有無
・税金や社会保険料の影響
いかがでしょうか。
年金の「繰り上げ受給」「繰り下げ受給」を判断するには様々な要素が複雑に絡み合い、なかなか一筋縄ではいかないことがご理解いただけたのではないでしょうか。
「繰り上げ受給」「繰り下げ受給」ともに、一度決定すると後から覆すことができないため、必要に応じて専門家に相談することも含め、慎重に検討すべきといえます。
[PR]ファイナンシャルプランナーが個別にご説明『NISAのはじめかた』
住宅ローン控除の仕組みと対象となる物件・対象外の物件を徹底解説