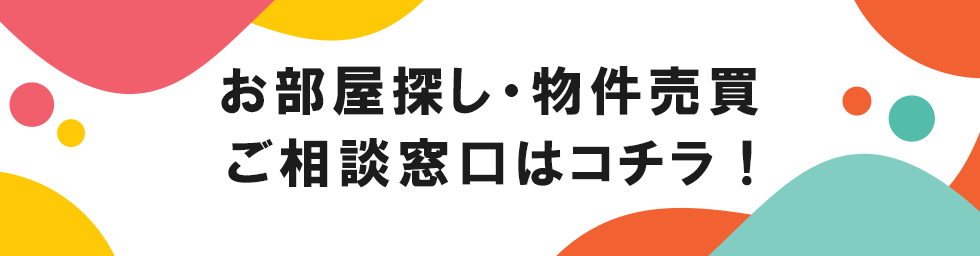保険年金
保険年金
保険金が突然ストップ!?交通事故と『症状固定』の知られざる落とし穴とは!?
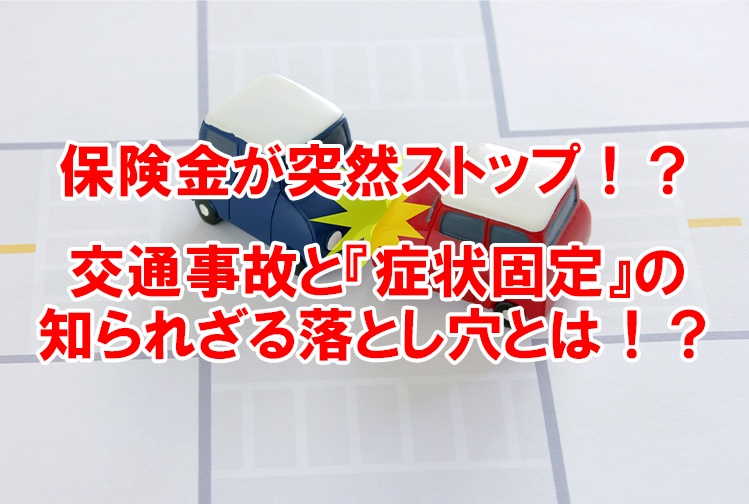
先日、著者の知人から、交通事故の保険金に関する相談を受けました。
冬の雪山でスリップ事故に巻き込まれ、まだ完治前(リハビリの途中)とのことですが、すでに保険会社から治療費の打ち切りを打診されているというのです。
この方は、交通事故への備えとして民間の任意保険にしっかり加入しており、その契約内容も、通院費や治療費はもちろん、精神的苦痛や休業損害、後遺障害への補償まで、一般に必要とされる範囲はすべてカバーできるものでした。
にもかかわらず、まだ完治していない段階で保険会社から打ち切りを告げられるとは、一体どういうことなのでしょうか。
実は、保険金支払いの実務では、「もらえると思っていた保険金が満額下りなかった」「思っていたよりも金額が少なかった」といったトラブルは決して珍しくありません。
原因はさまざまですが、今回のケースでは、いわゆる「症状固定」の解釈をめぐるものであり、実務上も非常に揉めやすいテーマの一つです。
この概念について最低限の知識がないと、被害者が一方的に不利な立場に追い込まれてしまうことも少なくありません。(今回は、推測できる保険会社の思惑をお伝えしたうえで、一般的な対抗措置や、必要に応じた第三者機関・弁護士への相談をアドバイスさせていただきました)
そこで本稿では、交通事故に関する保険金請求でトラブルになりやすい「症状固定」の意味と、それに対する対応策について、知っておきたいポイントを分かりやすくご紹介していきます。
■「症状固定」とは?——治ったかどうか、ではない
まず大前提として押さえておきたいのは、原則として保険金の支払いは、「完治または症状固定まで」とされているケースが多いということ。
言い換えれば、保険会社には「完治」まで治療費を払い続ける義務はないということです。
では、「症状固定」とはどんな状態なのでしょうか?
症状固定とは、「これ以上治療を続けても症状の改善が見込まれない状態」を指します。
たとえば、まだ患部に痛みやしびれなどの症状が残っていたとしても、現状が「回復の限界」とされた場合、その時点で症状固定と判断されることになります。
ここで問題になるのが、何を以って「回復の限界=症状固定」と判断するかです。
本来は、「医師の見解(医学的見地)」「本人の証言(自覚症状)」「客観的なエビデンス(レントゲン・MRI画像等)」などを前提にしっかり話し合いを行い、医師や本人の同意と納得を得たうえで、症状固定の可否を総合的に判断することが望まれます。
しかし、実務では「この怪我は通常〇ヵ月で症状固定としています」「社内で検討した結果、今月一杯とさせていただきます」といった、保険会社からの一方的な通告により「症状固定=保険金の打ち切り」となってしまうケースも珍しくないのです。
■なぜ保険会社は「症状固定」を急ぐのか?
なぜ、保険会社は急いで「症状固定」と判断したがるのでしょうか?
それは、保険金の支払いを早く打ち切りたいという経済的な思惑があるからに他なりません。
保険会社にとって、交通事故の被害者が長期間にわたって治療を続ければ続けるほど、支払うべき保険金額は膨らんでいきます。
とくに、通院費・交通費・休業損害などは、治療の継続期間に比例して増えるため、経営上のリスクと見なされやすいのです。
もちろん、すべての保険会社が不誠実というわけではありませんし、保険会社も過剰な医療行為や虚偽証言を看破し、これを抑止すべき難しい立場にあることも事実です。
しかし、冒頭のケースのように、「まだリハビリ中なのに突然治療費が打ち切られた」といった声があることも事実であり、実際に裁判に発展するケースも散見されます。
少なくとも、被害者としては保険会社の対応には、一定の警戒心・猜疑心を以って臨むべきであるとはいえるでしょう。
■被害者側にできることはあるのか?
では、もし保険会社から一方的な「打ち切り宣言」を受けてしまった場合、どんな対抗措置が可能なのでしょうか?(後遺障害認定を狙う方法もありますが、話が複雑になってしまうため、本稿ではそれ以外の方法をご説明します)
まずは、「症状固定」の判断根拠の開示請求と、「医師の見解(医学的見地)」「本人の証言(自覚症状)」との齟齬を整理して伝えることが第一段階です。
保険会社としても、症状固定の判断が苦情やクレームの原因となりやすいことは承知していますし、形式的な打ち切りではかえってトラブルの火種となる可能性があることも理解しています。
たとえば「医師(主治医)が治療継続の妥当性を発言している」「本人の自覚症状が回復傾向の途中にある」といった事実があれば、そうそう無碍には出来ないはずです。
それでも保険会社が話し合いに応じない場合(担当者が電話に出ず折り返しもない、一切の聞く耳を持たず話し合いにならない等)には、本社のお客様相談室や日本損害保険協会の運営する「そんぽADRセンター」のような第三者機関への相談が第二段階となります。
特に、そんぽADRセンターでは、専門の相談員による損害保険や交通事故に関する相談を原則無料で受けられるうえ、相談内容によっては保険会社へ苦情内容の通知とその解決の仲裁をしてもらえる場合もあります。
トラブルの初期段階では、非常に頼りになる存在といえるでしょう。
ここまで対抗措置をとっても解決しない場合、いよいよ第三段階として弁護士相談を検討することになります。(もちろん、ご自身でのやり取りに不安がある場合には、途中段階を飛ばして弁護士相談でもよいでしょう)
弁護士に依頼する場合、相応に費用が発生しますが、契約内容に「弁護士費用特約」を付けていれば、その全額または一部が保険適用になる場合もありますので、不安な方は特約の追加も是非チェックしてみてください。
いかがでしょうか。
保険は、契約内容に基づく“交渉ごと”の側面も強く、専門知識を持つ側(=保険会社)が優位に立ちやすい構造になっています。
だからこそ、被害者側も必要な知識を持ち、時には専門家の助力を得ながら、自身の権利を守る姿勢が必要不可欠です。
「症状固定」という言葉に惑わされず、自分の体の状態を正しく伝え、納得のいく補償を受け取る――。そのための一歩として、本稿が参考になれば幸いです。