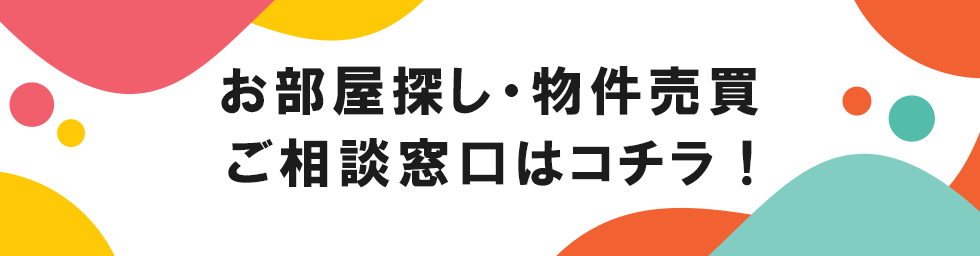ライフ
ライフ
住宅セーフティネット法が10月より改正!終身建物賃貸借契約は広がるのか!?

高齢者の住宅確保が社会的な課題となって久しい昨今、不動産業界にとっても大きな影響を与える法改正が迫っています。
いまや日本は、超高齢社会のまっただ中。とりわけ単身高齢者の増加が顕著で、国土交通省によれば2030年には900万世帯近くに達する見通しです。
しかし現実には、こうした高齢者や生活困窮者など、いわゆる「住宅確保要配慮者」が民間の賃貸住宅に入居することは容易ではありません。家賃滞納、孤独死、死亡後の残置物処理など、オーナー側のリスクが大きすぎるためです。
加えて、こうしたリスクを誰がどう負担するのかをめぐっては、借地借家法の構造的な問題や、それを補強するような判例の存在もあり、オーナー側の「貸したくても貸せない」状況が続いてきました。
そうした背景を踏まえ、2025年10月(令和7年10月1日)より、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」が改正されます。
----------------------------------------------------
【参考】国土交通省ホームページ
『住宅セーフティネット法等の一部を改正する法律について』
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000055.html
----------------------------------------------------
今回はこの法改正の背景と内容、そして今後の実効性について、不動産オーナーの視点からわかりやすく整理してみたいと思います。
■高齢者に貸したくても貸せない――制度と現実の深いギャップ
近年、単身高齢者世帯は急増しており、2030年には900万世帯に迫るとも推計されています。持ち家率の低下もあいまって、高齢者による賃貸住宅への居住ニーズは高まり続けているのは間違いありません。
その一方で、貸主となるオーナー側はといえば、こうした入居希望者に対して極めて慎重な姿勢を取らざるを得ない状況です。
理由は明白で、家賃滞納や孤独死、死亡後の残置物処理、相続人との交渉といった一連の事態に対し、現在の制度ではオーナーのリスクがあまりに重すぎるためです。
たとえば、借主が死亡した際、契約は当然に終了せず、法的には相続人全員に解除通知を送らなければならないケースもあります。こうした煩雑な手続きが発生するうえに、誰が相続人かもすぐにわからないとなれば、その間に空室が長期化し、家賃収入も止まります。
こうした「制度的な不備」の根源には、借主保護を徹底する借地借家法の存在と、それを支持する司法判断が挙げられます。
賃貸住宅は本来、契約自由の原則に基づくものであるべきですが、現実には“貸すと戻ってこない”“貸した人が亡くなってもすぐに契約が終わらない”という恐れから、オーナーが二の足を踏む事態となっているのです。
■「終身建物賃貸借契約」の制度見直し――解決策となるか?
こうした課題への対応策の一つとして、今回の法改正で注目されているのが、「終身建物賃貸借契約」の活用促進です。
この契約は、賃借人の死亡をもって契約が終了する形式の賃貸借契約で、相続によって賃借権が承継されないのが最大の特徴です。つまり、借主が亡くなった時点で契約は自動的に終了し、オーナーは速やかに部屋に立ち入り、次の入居準備に入ることができます。
これにより、契約終了の曖昧さや残置物処理の遅れといった問題が大幅に軽減されることが期待されています。
従来は、この契約を活用するには住宅ごとに都道府県知事の認可が必要であり、物件情報・間取り図・バリアフリー要件などを満たしたうえで個別に申請するという煩雑な手続きが必要でした。
今回の法改正では、この認可方式を「住宅単位」から「事業者単位」へと切り替え、事務負担や時間的ロスの軽減が図られます。また、認定保証業者の導入や見守りサービスとの連携強化もあわせて掲げられています。
■制度は変わっても、“貸す側の本音”は変わるのか
では、今回の法改正・制度変更によって、こうした課題は解決されるのでしょうか?
結論からいえば、課題解決に繋がるとは考えにくく、その影響はごくごく限定的なものに終わるのではないかと、著者は考えます。
たしかに、終身建物賃貸借契約によって死亡後の対応は明確になりましたが、それ以外のリスク――滞納、騒音、トラブル対応、保証人(緊急連絡先)不在、残置物の所有権問題――といった懸念はまったく軽減されていません。
制度として認定保証会社や見守りサービスの整備が開始されるものの、どこまで実効性が伴うものかは不透明で、そこから“外れた部分”はオーナーが無限責任を負う構造は維持されたままなのです。
さらに言えば、物価高により運営コスト(修繕費・管理費等)が高騰する一方、家賃への転嫁が進まず収益性低下が進む昨今の賃貸市場において、あえてリスクの高い入居者を受け入れる余力はないというのが、多くのオーナーの正直な声でしょう。
本当に制度を機能させたいのであれば、借地借家法そのものを見直し、「オーナー側の責任範囲を“有限”にする」改革が不可欠です。
入居者保護の理念は大切ですが、それが貸主の“無限責任”のうえに成り立っているうちは、誰もこの課題の本質には手をつけていないと言わざるを得ないでしょう。
いかがでしょうか。
2025年10月に施行される住宅セーフティネット法の改正は、確かに制度面での一歩前進といえる内容を含んでいます。
しかし、「制度が整ったからといって貸す側の心理がすぐに変わるわけではない」――この現実を見落としてはなりません。
高齢者や要配慮者の住宅確保を本気で進めたいのであれば、制度設計の根本に立ち返り、「貸主・借主双方にとって現実的で安心できる環境づくり」が求められているのではないでしょうか。