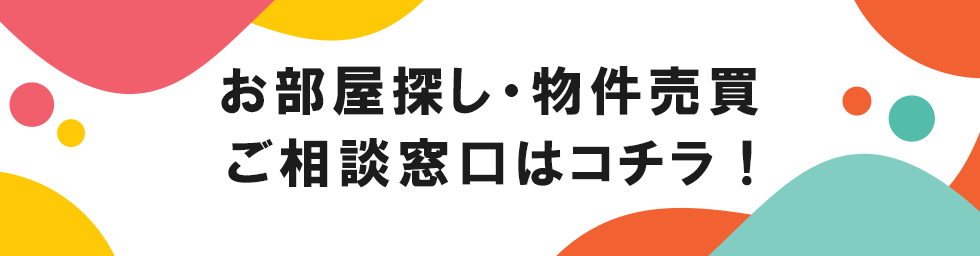ライフ
ライフ
高速バス「相席ブロック」は裏技ではなく迷惑行為――利用者全体に跳ね返る問題とは!?

近年、高速バスを巡って「相席ブロック」と呼ばれる行為が問題視されています。
隣り合う2席、場合によってはその前後をまとめて予約し、直前に1席を残してキャンセルする。こうして隣席を空席にして、自分だけでゆったり座る――一部ではこの手口が「裏技」としてSNSで拡散されています。
一見すると単なる個人の“お得術”に見えるかもしれません。しかし、バス会社にとっては看過できない大きな問題です。わずか数名の利用者がこの方法を繰り返すだけで、キャンセル率は跳ね上がり、稼働率は低下します。収益は圧迫され、最悪の場合は路線廃止や経営そのものが揺らぎかねないのです。
背景には、従来の対面販売や紙チケットによる予約から、ネット予約中心へ移行したことがあります。スマートフォンで簡単に購入・キャンセルできる利便性の裏で、モラルを欠いた行為も容易になり、さらにSNSを通じて「ちょっと得する方法」として広まってしまった。こうした構造こそが、この問題の本質といえるでしょう。
本稿では、この「相席ブロック」の実態と背景、バス会社への影響と法的リスク、そして今後の対策と課題について整理していきます。
■相席ブロックの実態と背景とは!?
「相席ブロック」とは、複数の座席をまとめて予約し、出発直前に不要な座席をキャンセルして空席を確保する行為を指します。なかには「予約だけして支払いを行わず、未払いによる自動キャンセルを狙う」パターンもあると報じられています。
いずれの場合も、キャンセル料の安さを逆手に取った行為です。多くの高速バス会社ではキャンセル料が100円前後に設定されており、利用者にとっては大きな負担になりません。そのため「どうせ安いから」と安易に繰り返されやすいのです。
こうした行為は、SNS上で「ちょっとした工夫で快適に移動できる方法」として拡散されています。しかし、実態は明らかに“迷惑行為”にほかなりません。予約上は満席に見えても実際には空席が生じ、他の利用者が乗車できないまま出発することになる。人気路線で「満席表示なのに座席がガラガラ」という状況が生まれるのも、この悪質行為の影響といえます。
■バス会社への影響と法的リスクとは!?
相席ブロックは、事業者に深刻な負担を与えます。わずか数人の悪質利用者がいるだけで、キャンセル率が大きく変動し、稼働率は低下します。バス会社は収益を確保できず、結果的に運賃の値上げや路線の縮小といった形で、結局は一般利用者が不利益を被ることになります。
さらに、この問題はモラルだけの問題ではありません。報道によれば、悪質な場合には民事上の不法行為責任や、刑法上の「偽計業務妨害罪」に該当する可能性もあるとされています。著者は法律の専門家ではないため断定は避けますが、モラルを欠いた行為が法的責任につながりかねない点は利用者として理解しておくべきでしょう。
「相席ブロック」は決して“お得な裏技”ではありません。事業者の運営を妨害する行為であり、SNSで面白半分に紹介することすら、業務妨害の一端を担う危険性があるのです。
■今後の対策と残された課題は!?
では、この問題に対してどのような対策が考えられるのでしょうか。
第一に、キャンセル料の見直しです。西鉄バスの「はかた号」では、2023年に決済期限を当日へ短縮し、さらに2024年12月からは前日以降の払戻手数料を運賃の50%に引き上げました。こうした強化策は一定の抑止効果があると考えられ、他の事業者にも広がる可能性があります。
しかし、新幹線やLCCとの競争を考慮すると、すべての路線で一律にキャンセル料を高額化することは難しい現実もあります。利便性を失えば利用者が離れ、競争力が削がれてしまうため、事業者は難しい判断を迫られることになります。
第二に、予約システムの改善です。直前キャンセルを繰り返す利用者のアカウントを制限したり、後払い予約を制限したりする仕組みが有効と考えられます。ただし、こうしたシステムには開発・保守コストがかかり、最終的には運賃への転嫁が避けられません。
結局のところ、相席ブロックへの対策は「制度」と「モラル」の両面から進める必要があります。事業者の努力だけでは限界があり、利用者側の意識改革も欠かせないのです。
いかがでしょうか。
高速バスにおける「相席ブロック」は、便利さと低コストの裏で横行する迷惑行為です。キャンセル料の安さ、ネット予約の容易さ、そしてSNS拡散が結びつき、一部の利用者が繰り返し悪用する状況を招いています。
こうした行為はバス会社の経営を圧迫し、最終的には運賃値上げや路線廃止といった形で、一般利用者に跳ね返ります。モラルの欠如にとどまらず、場合によっては法的責任を問われるリスクもあることを忘れてはなりません。
キャンセル料の見直しや予約システムの強化といった対策は進むでしょうが、それに伴うコストは結局、多数の善良な利用者に転嫁される可能性が高いのです。
利便性と秩序をどう両立させるか。公共交通の持続可能性を守るために、事業者と利用者の双方に冷静な判断と責任ある行動が求められているといえるでしょう。