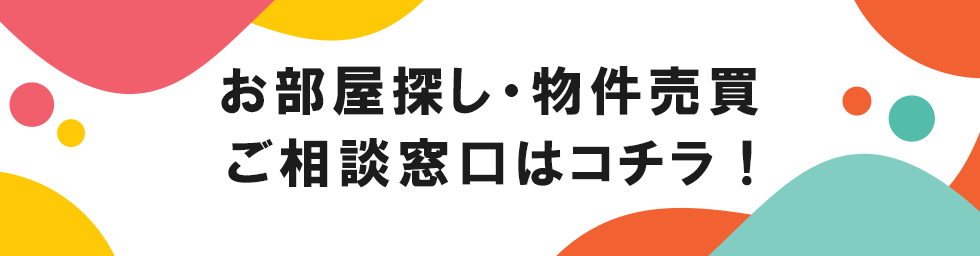ライフ
ライフ
「静かな退職」がブームに。なぜ「やる気を出すメリット」が失われたのか!?
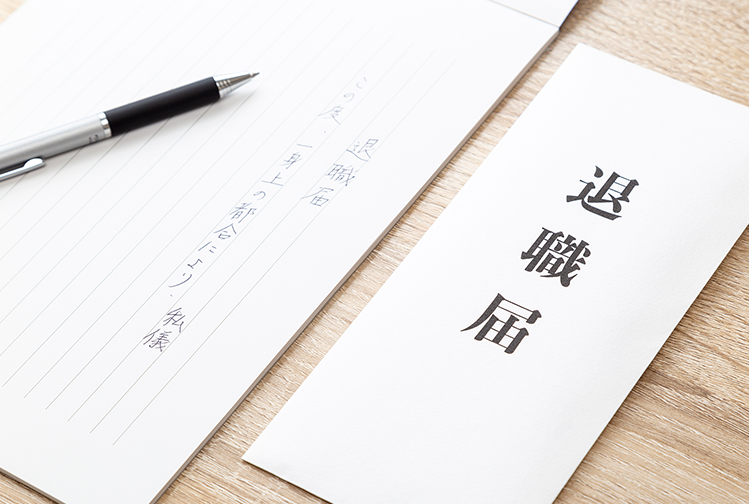
かつて「仕事に人生を捧げる」ことは、日本社会で美徳とされてきました。
努力を惜しまず会社に尽くせば、それなりの報酬と地位が手に入る──そんな前提が疑われることはほとんどありませんでした。
しかし近年、日本でも「静かな退職(Quiet Quitting)」という言葉がブームになっていることをご存じでしょうか?
「静かな退職」とは、「企業に勤める労働者が、積極的に退職はしないものの、必要以上の仕事をしない状態」を指します。
必要以上に本業へコミットすることを避け、個人の時間やキャリア形成を優先する生き方、「仕事=人生」という価値観から脱却しようとする動きが広がっているのです。
その背景には、単なる個人の意識変化だけでなく、社会構造そのものの変化があるとされています。
本稿では、「静かな退職」の背景にある日本の課題と、今後の動向について分かりやすくご説明していきます。
■成果主義の形骸化、報われない努力
日本企業では、成果を上げても報酬(給与や昇進)への影響はごくわずか、という現実が根強く存在しています。
たとえば、総合職の昇進レースにおいても、個人の能力やパフォーマンスより、年次や年功が依然として重視されるケースが少なくありません。
いわゆる「2:8の法則」に象徴されるように、一部の優秀な社員が、多数の社員(ときに上司すらも)を支えているにもかかわらず、待遇に明確な差がつかないのです。
この構造は、もともと日本型終身雇用・年功賃金モデルの延長線上にあり、バブル崩壊後も大きくは変わりませんでした。
また近年は、コンプライアンス意識の高まりにより、内部統制やハラスメント防止といった、直接的な利益を生まない管理業務や報告作業が肥大化しています。
厚生労働省による「ストレスチェック制度(2015年施行)」や、いわゆる「パワハラ防止法制(労働施策総合推進法の改正、2020年施行)」の導入も、こうした流れを後押ししました。
さらに、労働基準法の改正(いわゆる「働き方改革関連法」)により、時間外労働の上限規制が導入された結果、管理職ではない一般社員は長時間残業が物理的にできなくなっています。
このため、副業や自己研鑽に充てる時間的余裕は生まれた一方で、経験やスキルを「努力や時間で補う」という従来の働き方は通用しなくなりました。
こうした状況の積み重ねにより、優秀な社員は待遇に満足できず、一般社員はスキルや経験を積みたくとも時間的制約でそれもままならない──。
仮に理不尽を乗り越えて管理職に昇進したとしても、今度はパワハラ・セクハラリスクに怯えながら、残業規制の中で溢れる仕事を抱え込むことになります。
これが健全な労働環境であるかはさておき、少なくともこの構造では、やる気を出すインセンティブは失われて当然といえるでしょう。
■副業・スキルアップ志向と合理的なサバイバル戦略
こうした状況に対して、個人が取れる合理的な戦略のひとつが、「本業をセーブして副業や自己投資に注力する」ことです。
これが冒頭で触れた「静かな退職」ブームにもつながっています。
従来、多くの企業が労働者の副業を禁止していましたが、2018年に厚生労働省が策定した「副業・兼業の促進に関するガイドライン(※)」により、企業には副業・兼業を認める努力義務が課されました。
これも変化の追い風となったのでしょう。
(※)厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000962665.pdf
副業を行えば、仮に本業の給与が伸びなくても、収入源を複線化することが可能です。
副業収入が年20万円以下であれば確定申告不要(※一定条件を満たす給与所得者の場合)で、社会保険料も本業ベースで決まるため、手取り効率が良いケースもあります。
また、時間的余力を使って資格取得やプログラミング学習などに取り組み、成果主義の進む外資系企業やスタートアップへの転職、あるいは起業を視野に入れる動きも活発化しています。
すべては、リスクとリターンを冷静に見極めたうえでの合理的なサバイバル戦略です。
本業に過度な期待を抱かず、自らの市場価値を高めながら未来を切り拓こうとする動きは、今後ますます主流になるでしょう。
■企業が抱えるリスク、人材流出と組織力の低下
しかしこの状況は、企業にとって大きなリスクを孕んでいます。
優秀な人材ほどこうした現実に早く気づき、より好条件の職場を求めて転職、あるいは起業のため早期に離職する可能性が高まります。
職場に残された管理職は疲弊を重ね、一般社員はモチベーションが上がらない──。そんな環境が続けば、企業としての競争力は高まるはずもありません。
企業側がこの現実を直視し、なぜ「静かな退職」がブームになってしまったのかを真剣に分析して改善する。
すなわち、これを労働者個人の我儘や怠慢と決めつけるのではなく、成果に応じた正当な評価や挑戦できる環境づくりに本気で取り組む必要があるのです。
この環境変化に対応できなければ、「静かな退職」はさらに広がり、長期的には日本企業の国際競争力が失われていく恐れもあるでしょう。
いかがでしょうか。
「静かな退職」の背景には、単なる個人のモチベーション低下ではなく、社会・企業構造そのものの歪みがあります。
努力が報われず、リスクばかりが増える本業に過度な期待を抱くよりも、リスク分散を図り、自らの生存戦略を考える──。それはごく自然な流れといえるでしょう。
いま求められているのは、個人が合理的に自分を守る選択を尊重し、企業側も「成果が正当に報われる仕組み」を再構築することです。
そうでなければ、静かな退職の波はさらに広がり、日本社会全体の活力を奪っていくことになりかねません。
「静かな退職」のブームには、そんな未来への警鐘が鳴り響いているのかもしれませんね。