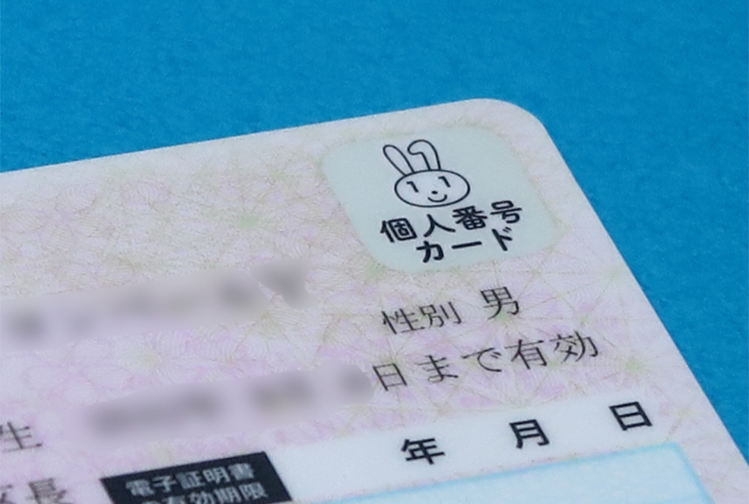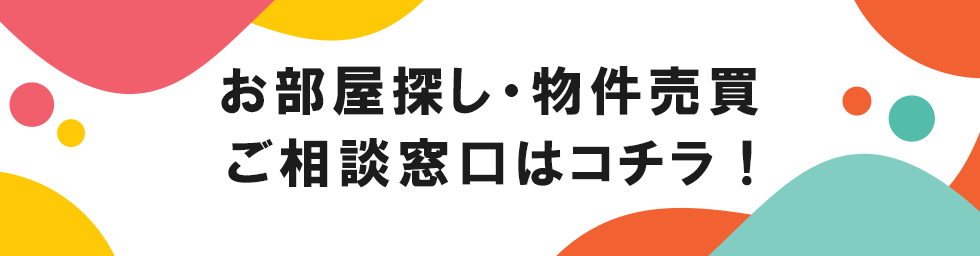節税
節税
生命保険料控除が2026年度だけ拡充!ほとんど意味のない制度の実態を解説します!
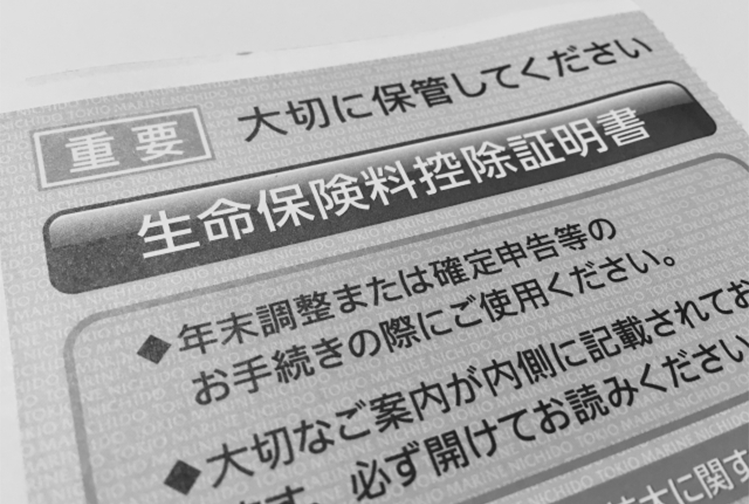
秋も深まり、そろそろ生命保険会社から「保険料控除証明書」が届き始める時期。年末調整や確定申告の季節になると、「ああ、またこの書類か」と感じる方も多いのではないでしょうか。
しかし、今年のこの通知には、少し“先取りして知っておきたい”ニュースが隠れています。
それは、2026年(令和8年)分の所得税において、生命保険料控除が一部拡充されるという制度改正です。
しかも、その拡充対象は「子育て世帯」に限られ、期間もわずか「1年間」限定。対象世帯も期間もかなり絞った制度改正なので、「さぞやお得な効果があるのでは!?」と期待する方も多いかもしれません。
実は、そうした反応こそが政府の思惑です。よくよく拡充内容を確認すると、多くの人がイメージする“減税メリット”とは真逆の性格をもつ制度であることが浮かび上がってきます。
本稿では、この“2026年限定の控除拡充”について、「制度の仕組み」「背景」「実質的な効果」の観点から、分かりやすく整理してみたいと思います。
■そもそも、生命保険料控除とはなにか!?
まずは、そもそも「生命保険料控除」とはどんな制度なのかについて、簡単におさらいしておきましょう。
生命保険料控除とは、支払った保険料の一部を所得から差し引く(控除する)ことで課税所得を減らし、税金負担を軽くする制度です。
対象となるのは、「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3種類で、「新契約」と呼ばれる平成24年1月1日以後に締結した保険契約等の場合、以下のように控除上限額が決められています。(より詳細な条件は、国税庁のホームページ等でご確認ください)
-----------------------------------------------------
<新契約の控除上限額>
・一般生命保険料:4万円
・介護医療保険料:4万円
・個人年金保険料:4万円
※合計で最大12万円まで控除が受けられます。
-----------------------------------------------------
今回の改正では、23歳未満の扶養親族を有する子育て世帯を対象に、2026年分に限り、一般生命保険料の控除上限額が「4万円」→「6万円」に引き上げられます。
ただし、全体の控除合計額は最大12万円で据え置かれているため、一般生命保険料控除で6万円の適用を受ける場合、介護医療保険や個人年金保険の控除額が減少することになります。
■拡充の目的は子育て支援!?――しかし本質は“予算を使わない政策”
では、今回の改正目的はどこにあるのでしょうか。
財務省によると、「子育て支援に関する政策税制」の1つとして位置づけられています。
また、その改正理由として、『子育て世帯は、安全・快適な住宅の確保や、子どもを扶養する者に万が一のことがあった際のリスクへの備えなど、様々なニーズを抱えており、税制においてこうしたニーズを踏まえた措置を講じていく必要がある』と説明されています。
-----------------------------------------------------
<参考>
・財務省ホームページ『令和7年度税制改正の大綱』
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/07taikou_mokuji.htm
・同、『令和7年度税制改正の解説』
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/explanation/index.html
-----------------------------------------------------
しかし、詳しく中身を見れば、こうした説明が建前にすぎないことは明らかです。
実際には、子育て世帯の「リスクへの備え」を促すような実効性はほとんどなく、財源をほぼ増やさずに“支援策を打ち出したように見せる”ための設計と考えるのが自然です。
対象を子育て世帯に限定したのも、必要な財源を極小化するため。そのうえで「支援策を増やした」というアピール材料を得る――まさに、“予算を使わない子育て支援”といってよいでしょう。
■実際の恩恵はごく僅か!?複雑な制度設計に隠された実態とは!?
では、子育て支援政策として見た場合、実際のところどのような効果があるのでしょうか?
結論から言えば、「体感できる効果はほぼない」のが実態です。
「23歳未満の扶養親族がいる世帯」に限定されている点は制度趣旨から止むを得ないとしても、肝心の子育て世帯にとっても、その恩恵はごくごく軽微です。
今回の拡充によって増えるのは「税額控除」ではなく「所得控除」。住宅ローン減税のように税金そのものが減る仕組みではなく、「課税対象となる所得」が減るだけです。たとえば、所得税率20%の人であれば、控除枠が2万円増えても減税額はわずか4,000円(1ヵ月あたり約333円)にすぎません。これでは、万一の備えとして保険契約を新たに検討する動機づけには到底ならないでしょう。
さらに、全体の控除合計上限(12万円)は据え置かれているため、他の控除を利用している世帯では減税効果が相殺される可能性が高い。結果として恩恵を実際に享受できるのは、他の控除を使っておらず、かつ生命保険料を多く支払っているごく一部の世帯に限られます。
つまり、今回の拡充は「対象も効果も極めて限定的」であり、“子育て支援の看板を掲げた政治的パフォーマンス”といっても過言ではないのです。
いかがでしょうか。
2026年限定の生命保険料控除拡充は、確かにニュースとしての話題性はありますが、実際に家計に与える影響はごくわずか。「子育て支援」という美名のもとで制度が設計されてはいるものの、その実態は一部の世帯にしか効果が及ばず、減税額もほぼ誤差の範囲です。
「万が一のリスクに備える」という政策目的を掲げながら、実際には財源をほとんど使わずに支援策を“増やしたように見せる”制度になっている点が問題なのです。
さらに言えば、「所得控除」と「税額控除」の違いを理解する人は多くなく、印象操作によって「4万円→6万円に拡充」というキャッチーな見出しだけが独り歩きする――それこそが、この改正の最大の“狙い”かもしれません。
本来、真に実効性のある子育て支援策とは、こうした限定的な減税ではなく、教育・医療・住居といった生活基盤そのものを下支えする仕組みであるはずです。
高市新総裁のもと、来年度以降の税制改正がどの方向へ進むのか――その姿勢が早速問われるテーマの一つといえるでしょう。