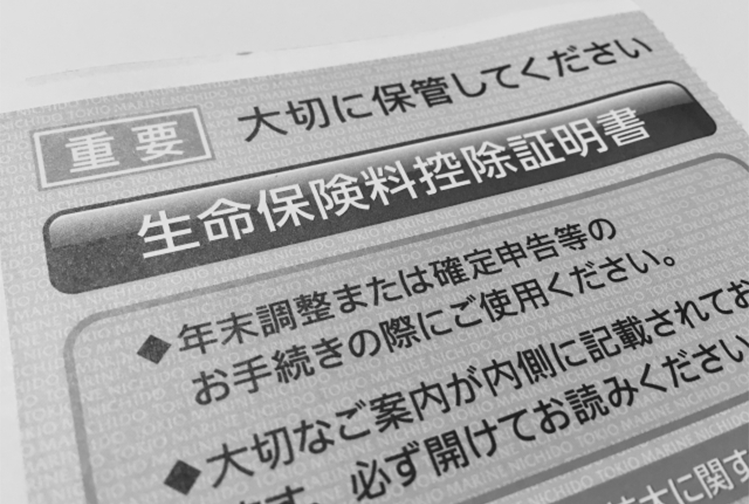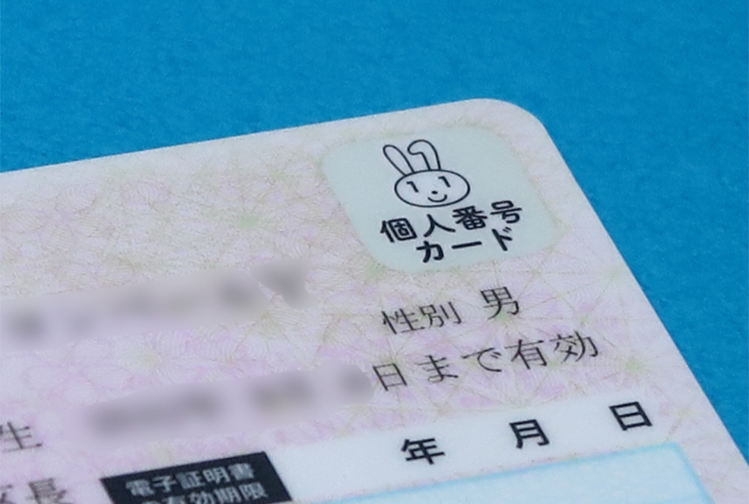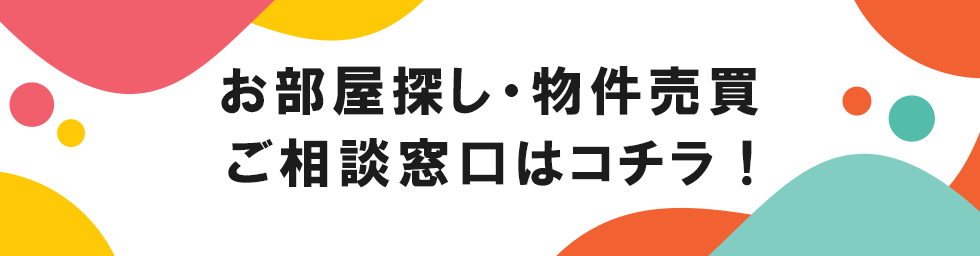節税
節税
独身税?社会保険料頼みの少子化対策が危うい理由とは!?

ここ最近、「独身税」という言葉を、よくSNS等で見かけるようになりました。その差別的な名前に思わずぎょっとする方も多いことでしょう。
もちろん、実際にそんな名前の税金があるわけではありません。正しくは、「子ども・子育て支援金」という名称で2026年度より新設される、少子化対策を目的とした特定財源の一つです。
---------------------------------------------------------
<参考>こども家庭庁ホームページ『子ども・子育て支援金制度について』
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin
---------------------------------------------------------
ご承知のとおり、我が国の少子化は止まる気配がありません。その一方で高齢化は着実に進んでおり、少子化対策の必要性・重要性に多くの日本国民が賛成しているのは間違いありません。
それにもかかわらず、この支援金制度が「独身税」と揶揄されるのはなぜでしょうか。著者の見るところ、制度そのものへの反発というよりも、「財源を税金や国債でなく社会保険料に頼ったこと」「実質的に国民負担は増えないといった説明を繰り返していること」「棒読みとの批判も出た大臣答弁が国民の不信を強めたこと」といった進め方への不満が背景にあると考えられます。加えて、この制度を担う子ども家庭庁に対する“不要論”が収まらない現状も、「独身税」という呼称を広める一因になっているのでしょう。
本稿では、この「独身税」、すなわち子ども・子育て支援金制度がなぜここまで批判の的となっているのか、本来どう進めるべきであったのかを考えていきます。
■社会保険料を財源にする発想の危うさ
子ども・子育て支援金制度の最大の特徴は、その財源を「税」や「国債」ではなく「社会保険料」に求めている点です。
本来、社会保険料は給付と負担の対応関係を前提とする仕組みであり、年金・医療・雇用といった分野がその典型です。ところが今回の制度では、既婚・未婚を問わず、子どもがいる世帯も含めて国民全体に「保険料」という名目で追加負担を求めています。
実態としては増税と大差がないにもかかわらず、あえて「保険料」と呼ぶことで抵抗感を和らげようとする。そこに多くの国民が不信感を抱くのは自然なことです。しかも社会保険料は税に比べて逆進性が強く、中低所得層にとって負担が重くなりやすい。少子化対策の必要性に賛同する人であっても、その原資を最も生活に余裕のない層に押し付けるのでは、政策の正当性が揺らぎかねません。
■「国民負担は増えない」という説明の詭弁
さらに国民不信を増幅させているのは、政府がこの制度について「新たな国民負担は生じない」と繰り返し説明している点です。担当大臣のみならず、首相までもが「医療・介護分野の歳出改革や賃上げによる社会保険料負担軽減効果の範囲で制度を構築する」と発言しています。
しかし、実際に支払う社会保険料が増える以上、それは明確な「負担増」です。政府の説明をそのまま受け入れたとしても、本来であれば減額されるはずの社会保険料が据え置かれるにすぎませんし、実際には「歳出改革」や「賃上げ」が予定どおり進むかどうかも不透明です。
そもそも「改革や賃上げが進めば負担感は軽減される」という論理は、裏を返せばそれらが実現できなければ即座に追加の負担増へと跳ね返るということです。将来の不確実な前提に依存した説明は、国民にとって安心材料どころか、不安を増幅させる要因でしかありません。
誤解を恐れずに言えば、こうした説明を真に受けている国民はほとんどいないでしょう。必要だったのは「正直に負担増をお願いする」ことと、その先にある政策効果の提示でした。にもかかわらず「増税ではない」「負担は増えていない」といった説明を繰り返すほど、国民の不信感は強まる一方だったのです。
■子ども家庭庁不要論と「独身税」
そして、この議論は子ども家庭庁そのものへの不信にも直結しています。子ども家庭庁は「子育て政策の司令塔」として設立されましたが、発足から時間が経つにもかかわらず少子化の流れを変える兆しは見えていません。巨額の運営費や人件費がかかっているにもかかわらず、その成果は国民に十分伝わっていないのが実情です。
「この省庁の運営費をそのまま子ども手当として配った方が、よほど実効性があるのではないか」という声も根強くあります。加えて、担当大臣が国会で棒読みと批判される答弁を繰り返すたび、「お飾りポストではないか」との不満が広まりました。
そのうえで、今回の制度が俗に「独身税」と呼ばれつつ社会保険料として導入されるのですから、国民が制度そのものだけでなく、子ども家庭庁の存在意義にまで疑問を抱くのは当然です。制度をわかりやすく整理し、信頼を得るべき司令塔が、逆に不信感を増幅させてしまっているのです。
いかがでしょうか。
「独身税」と揶揄される子ども・子育て支援金制度は、少子化対策の必要性という大義名分を持ちながら、その財源設計と説明の仕方によって国民の信頼を失いました。
社会保険料という形式を用いて実質的な増税を覆い隠し、「国民負担は増えない」と強調する政府。そして成果が見えにくい子ども家庭庁の存在。これらが重なり合い、制度への批判が「独身税」という呼称につながったのです。
少子化対策の重要性を否定する人はいません。しかし、国民に納得感を与える制度設計や説明がなければ、いくら新制度を導入しても信頼は得られません。必要なのは負担のすり替えではなく、正面からの議論と誠実な説明ではないでしょうか。