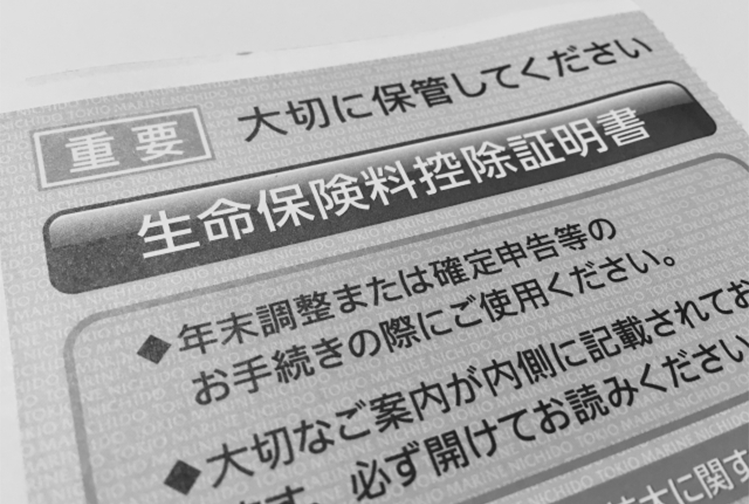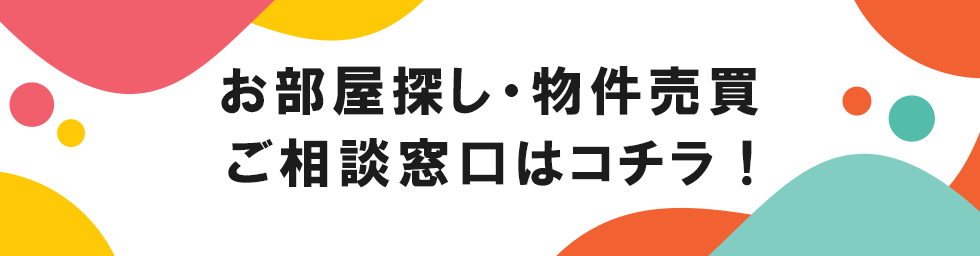節税
節税
確定申告「ID・パスワード方式」が廃止へ!?マイナンバー依存に潜むリスクとは!?
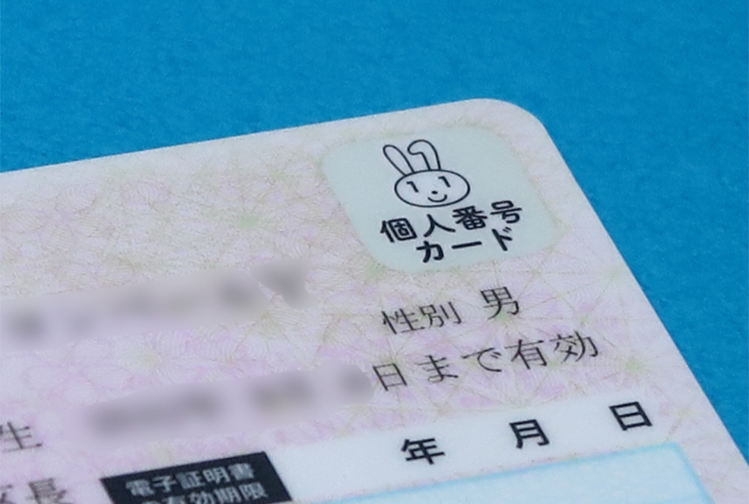
先日、国税庁より、確定申告における「ID・パスワード方式」の新規発行を停止する方針の発表がありました。マイナンバーカードを持たない人にとって、この方式は唯一のオンライン申告手段であったため、SNS等では失望の声が出始めています。
--------------------------------------------------------
<参考>
国税庁e-Taxホームページ内『ID・パスワードの新規発行停止について』
https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/2025/topics_20250925.htm
--------------------------------------------------------
ID・パスワード方式とは、税務署が本人確認を行った上で発行するIDとパスワードを利用し、マイナンバーカード不要でe-Taxによる申告を可能とする仕組みのこと。マイナンバーカードが手元に届くまでの暫定措置としてだけでなく、後述するような理由により“意思を持って”マイナンバーカードを持たない方にも、広く活用されてきました。
ところが、マイナンバーカード保有率が約8割に達し、マイナンバー方式の活用が増加していることを表向きの理由に、「ID・パスワード方式は廃止を含めて2025年中に結論を出す」ことが決まり、これに先行する形で冒頭の新規発行が停止されることとなったのです。
廃止決定前に新規発行を停止するとは何ともおかしな話ですが、「マイナンバーカードを持っていないと、確定申告が不便になる」という方向で検討されていること自体も、納税者にとっては理不尽な話に違いありません。
本稿では、このID・パスワード方式の廃止をめぐる動きについて、現状の課題と政府の本音を分析していきたいと思います。
■暫定措置から一転、「切り捨て」へ
ID・パスワード方式は、もともとマイナンバーカードが普及するまでの暫定措置として導入されました。しかし、現実にはカードを「持たない」という意思を持つ人々にとって、極めて重要な選択肢となっていました。高齢者や地方在住者、あるいはカードに不信感を抱く層にとって、この仕組みがあったからこそオンライン申告が可能だったのです。
今回の新規発行停止は「カード保有率が上がったから」という説明で済まされていますが、実際には「カードを持たない人の利便を切り捨てた」という意味合いを持ちます。政府が強調する「暫定措置は役割を終えた」という説明は、制度を支えてきた利用者にとっては到底納得できるものではありません。
加えて、新規発行停止のタイミングにも疑問が残ります。廃止を含めた議論が2025年中に行われるとされているにもかかわらず、その前に一方的に新規発行を止めてしまうのは、国民的議論や合意形成を軽視している印象を与えかねません。
実際、「今年の確定申告で困る人が出るのでは」という声もSNSで見られ、周知不足も含めて混乱は避けられないでしょう。「国民の利便性よりもマイナンバーカード普及を優先した」と受け止められるのは当然です。
政府は当初、「マイナンバーカードを持てば便利になる」「行政コストが削減されて国民にも恩恵がある」と繰り返し説明してきました。しかし実際に進められてきた施策は「持たなければ不便になる」という方向ばかり。健康保険証に続き、今回の確定申告も同じ構図です。
もっとも、ID・パスワード方式には、セキュリティ上の懸念があったことは事実です。発行時こそ税務署での本人確認を要件としましたが、その後は一要素認証で、ユーザーによるパスワード変更もできません。近年、証券口座やクレジットカードで不正ログイン被害が急増していることを踏まえると、リスクが高いのは否定できません。加えて、パスワードの使い回しや安易な管理が横行すれば、悪用の余地が広がることも懸念されていました。
しかし、だからといって制度そのものを廃止するのではなく、二段階認証の導入やワンタイムパスワードとの併用など、改善策を講じる余地は十分にあったはずです。カード非保有者が2割もいる現状を考えれば、選択肢をいきなり取り上げるのは乱暴です。むしろセキュリティを強化し、安心して使える仕組みにすることこそ、行政の本来の役割だったのではないでしょうか。
ところが、今回も健康保険証と同様に、「不便を避けたいならカードを持て」と迫る形に終始しています。これでは国民の側から「恩恵」というより「強制」と感じられてしまいます。
【PR】頑張って稼いでも、税金でほとんど残らない——そんなあなたへ
■信頼を損なう制度運営
一方で、「マイナンバーカードを持てばよいだけなのに、なぜ反発するのか?」という意見も少なくありません。確かに行政効率化の観点からは、カードへの集約は合理的に映る面もあります。
しかし忘れてはならないのは、マイナンバーカード保有は導入当初から「任意」であると説明されてきたこと、そして制度の根底を成すはずの「情報は厳格に管理される」「万一漏洩があれば国が責任を負う」が必ずしも守られていないことです。ご承知のとおり、健康保険証や公金受取口座の誤登録など、紐付け誤りや管理不備が繰り返され、国民の不信感は払拭されていません。
さらに、カードを持つことでリスクが増えるという逆説的な状況もあります。紛失や盗難による情報漏洩、家族間トラブルでの悪用、オンラインでの不正利用など、現実的なリスクはゼロになりません。それにもかかわらず、政府はこうした不安を十分に説明せず、「持たなければ不便になる」という圧力で普及を進めています。
国民にとって必要なのは、便利さを体感できるサービスと同時に、リスクに対する明確な説明責任です。利便性より普及率、説明より責任回避――こうした姿勢が続けば、信頼は回復するどころか失われていくばかりでしょう。マイナンバー制度の真の課題は、国民を納得させるだけの「安心」と「実利」を提示できていない点に尽きるのです。
いかがでしょうか。
ID・パスワード方式は、マイナンバーカードを持たない人々にとって重要な選択肢でしたが、実際にはカード普及の道具にされてしまった感が否めません。
マイナンバーカードを「持たないと不便になる」制度から、「持てば便利で安心できる」制度へ。政府が本当に取り組むべきは、そこに尽きるのではないでしょうか。