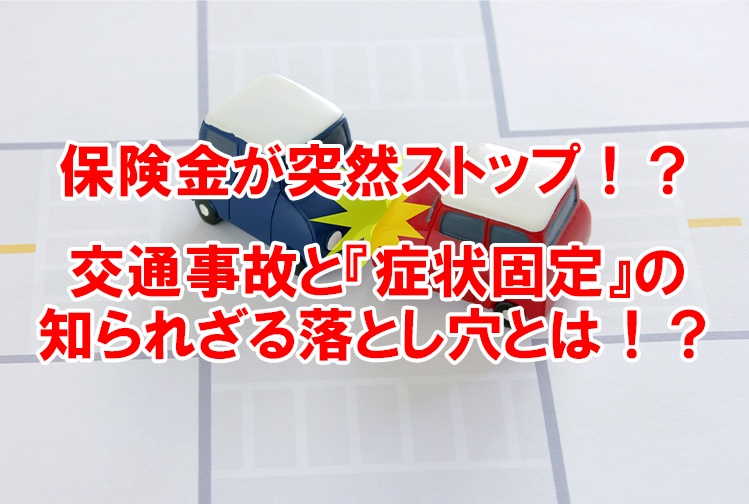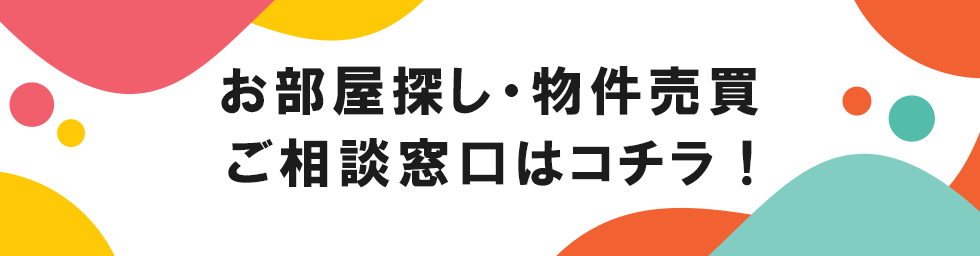保険年金
保険年金
こんな理不尽ある!?火災で保険金をもらったら税金で大赤字!?

火災保険といえば、アパートやマンションを経営するオーナーにとって「万一の備え」として欠かせない存在です。建物が火事で一部消失しても、保険金を受け取って復旧工事を行えば、とりあえず元に戻せる――多くの方がそう考えているのではないでしょうか。
しかし実際には、復旧できるだけの保険金を受け取ったにもかかわらず、工事後に手元資金が不足し、場合によっては借入を起こさなければならないケースが往々にして発生します。
詳細は本文にて後述しますが、保険金は「雑収入」として一括で課税される一方、復旧にかかった費用は「資本的支出」とされ、数十年にわたって少しずつしか経費化できず、税金を支払うための現金余力が枯渇してしまうことがあるためです。
この状況は、税金の仕組みを理解すれば道理にかなったものである一方、一般的な感覚からは受け入れがたく、「あまりに理不尽ではないか」「何のための保険なのか」と感じる方も少なくないことでしょう。
そこで本稿では、この理不尽な仕組みの背景と現実的に不動産オーナーが直面し得る影響、さらに同様のリスクが潜む事例について整理し、備えておくべきポイントを分かりやすくご説明します。
■保険金と復旧費用がズレる理由とは!?
火災で建物が損傷した場合、受け取る保険金は税務上「雑収入」として一括で計上されます。これは一時的な臨時収入であるため、その年の利益に丸ごと加算されるのが原則です。
もし、5,000万円の保険金に対して、5,000万円の復旧工事の支払いが全額工事当年度の経費として認められるのであれば当該保険金は実質ゼロ円となり税金は発生しません。一般的な感覚からすると、これをイメージする方が多いことでしょう。
しかし、不動産経営の現場では、こうした火災等による建物復旧工事は、1年間に全額を経費計上できる「修繕費」として計算するのではなく、数十年に渡って経費計上する「減価償却」の手続きによって計算するケースが多くあります。(個別案件ごとに、税理士や税務署に相談しながら判断することになります)
たとえば、火災による木造アパートの一部焼失に対する保険金5,000万円を受け取ったケースを考えてみましょう。(計算をシンプルにするため、法人税率30%と仮定、その他条件は考慮しないものとします)
木造アパートの法定耐用年数は22年。保険金と同じ5,000万円を全額復旧工事に支払ったとしても、工事当年度に経費計上できる金額は約227万円(5,000万円÷22年)に過ぎません。
そのため、工事当年度の法人税は、約1,432万円((5,000万円-227万円)×30%)にも及びます。
一方で、保険金5,000万円は工事業者に支払済のため、不動産オーナーは自腹で1,432万円の納税資金を準備しなければなりません。現実問題として、こうした纏まった現金の用意は難しいことも多く、金融機関から借り入れを起こして納税しなければならないケースが発生する、というわけです。
■銀行や決算に与える“見えない影響”とは!?
このように、実際には保険金を受け取り、その保険金で復旧工事をしただけなのに、税務処理上は「黒字なのに現金がない」という“ねじれ現象”が発生します。
そして、この問題は納税資金の不足だけにとどまらず、今後の融資戦略にも支障をきたす恐れがあります。
金融機関から見た際、決算書の利益が大きく計上される一方で、手元資金は借入で補っている状況は、少なくとも表面的には「資金繰りに余裕がない」「キャッシュフロー管理に難がある」と映りかねないからです。
当然、銀行員もこうした税務の仕組みは理解していますが、特に初めて取引する金融機関であれば、決算書の詳細を読み込んだり、オーナーに説明の機会を設けたりしてくれるとは限りません。表面的な数字だけでNG判断されてしまうリスクもあるでしょう。
また、事情を理解してもらったとしても、「納税資金を借り入れで賄った」という事実が不問とされるとは限りません。担当者や支店長がOKと判断しても、オーナーが直接説明できない本店審査部の判断で覆されるリスクも残るでしょう。
不動産オーナーからすれば理不尽な話に違いありませんが、決算数字と資金繰りのギャップを抱え込み、次の融資戦略や資金調達に悪影響を及ぼす“可能性”がある、ということは予め理解しておくべきといえます。
なお、同様な事象は、水害や地震による被害復旧、あるいは資産価値増加を伴う大規模修繕工事でも発生する可能性があります。
■投資家が備えるべき視点と対策とは!?
こうした理不尽を完全に解消することはできませんが、ダメージを和らげる工夫はいくつかあります。
まずは、税務の仕組み、とりわけ「減価償却」に関する知識を備えておくことです。特に扱う金額が大きな不動産経営においては、一般的な感覚で計算する(イメージする)納税額と、減価償却の手続きによる実際の納税額とでは、大きく乖離することも珍しくありません。
税理士や税務署に確認せずとも、概算の納税額くらいは自ら計算できるようになるとよいでしょう。
次に、発注する工事内容が、「修繕費(一括経費化OK)」なのか、「資本的支出(一括経費化NG)」なのかを知り、それぞれを分けて計上することです。
類似の工事内容であっても、資本的支出でなく修繕費として計上できる場合があり、修繕費の割合を増やせれば、税負担の軽減に繋がります。基本的に両者の区分は個別案件ごとに実態に応じて判断するため、このタイミングではむしろ税理士や税務署に積極的に相談するとよいでしょう。
最後は、不動産経営上、一定の「現金余力」は所持しておくことです。
不動産経営では、本稿で生じる不都合以外にも、突発的に纏まった現金が必要となるケースは存在します。そのため、普段から予備的な資金を積み立てたり、短期融資枠を確保しておいたりするのも現実的な備えといえるでしょう。
いかがでしょうか。
火災保険は確かに頼りになる備えですが、税務上のルールによって「保険金を受け取ったのに資金繰りが悪化する」という逆転現象が起きる可能性があります。理不尽に見える仕組みも、ルールを知って先に備えれば被害を最小化することはできます。
保険、税務、資金繰り、銀行説明――これらをワンセットで考えること。税や融資の視点も含めて備えてこそ、保険本来の役割が活きるといえるでしょう。