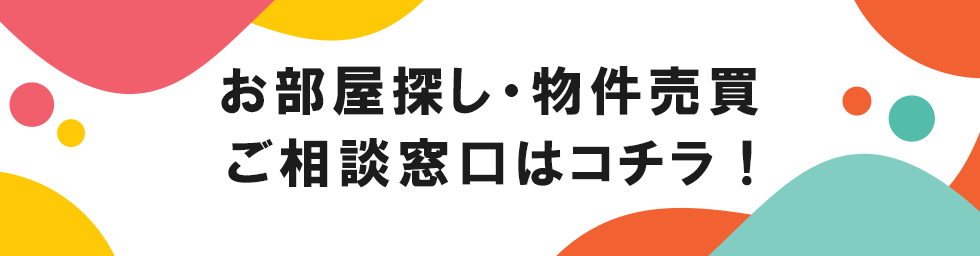資産運用
資産運用
投資信託等で用いられる平均利回りについて。2種類の計算方法を分析しよう

新NISAが2024年の1月から導入され、それにともなって資産運用を始めた方も少なくはないのではないでしょうか。資産運用にも様々な金融商品がありますが、長期間の運用とたくさんの資産への分散を行うには「投資信託」の利用が初心者にとっては非常に有効です。
投資信託とはたくさんの投資家から少しずつお金を集め、その資金を活用して投資のプロに運用を任せ、そこから得られた利益をそれぞれの投資家で分け合うという金融商品です。
しかし、投資信託には非常にたくさんの種類があり、現在日本で購入できる投資信託の数は6000種類近いといわれています。このようにたくさんの種類があると、投資信託を購入したいと思っても中々どの商品を購入していいのか判断が難しいのではないでしょうか。
投資信託を選択する上で抑えておきたいポイントはたくさんありますが、資産運用はお金を増やすのが目的なので、過去の運用結果から利回りはその中でも最も大切なポイントの一つです。よく「平均利回り」として過去数年間の利回りを平均したものが紹介されることがあります。
投資初心者の方だと、この平均利回りを「この利回りで毎年増えるもの」と思われる方が少なくありませんが、資産運用の世界では実際にはそううまくはいきません。では、この平均利回りとはどういう意味をさすのでしょうか。今回はこの「平均利回り」について詳しく見ていきましょう。
|
【INDEX】 ■利回りとは ■2種類の平均利回り ・算術平均 ・幾何平均 ■まとめ |
利回りとは
利回りとは一般的に、投資元本に対して1年間で得られる利益の割合のことを指します。例えば100万円を投資に回した場合、3%の利回りで運用することができれば、1年後には3万円の利益が得られるということです。資産運用はお金を増やすことが目的ですのでこの利回りを意識することは非常に大切なことです。
投資信託では運用の結果が毎年異なるので、この利回りも年によって変動します。また、投資信託はそれぞれの商品によってこの利回りの大きさも大きく異なります。なので自分がどれくらいの利回りを資産運用に求めているかによって投資信託を選択していく必要があります。
この過去の利回り等は証券会社のサイトや投資信託の目論見書(投資信託の説明書のようなもの)から簡単に調べることができるので参考にしてみてください。
2種類の平均利回り
数年間の利回りを平均した指標として「平均利回り」というものがあります。投資信託は毎年の利回りが変動するので、数年間の利回りの相場感を掴むことができるこの指標は非常に重要なものといえます。ただ、冒頭でも記載しましたが平均利回りの数値が毎年続き、その通りに資産が増えていくことはありません。また、平均利回りには2つの種類があり、どちらを使用しているかによって見え方が大きく異なります。
算術平均
一般的に利用され、イメージしやすい平均利回りが算術平均です。算術平均とは、数年間の一年分の利回りを足し合わせてその年数で割ることで計算することができます。例えば1年目の利回りが3%、2年目の利回りが5%だった場合にはその2年間の平均利回りは
(3%+5%)÷2年=4%
となります。この算術平均は非常にイメージがしやすいですが、資産運用の指標として利用するには少し劣っている部分があります。それは、同じ平均利回りでも各年の利回りが異なる場合には最終的な運用の結果に相違が出るということです。
例えば同じ平均利回り5%で各年の利回りが異なる2つの結果があったとします。
|
|
1年目 |
2年目 |
3年目 |
4年目 |
5年目 |
|
運用① |
+10% |
+5% |
-10% |
+10% |
+10% |
|
運用② |
-10% |
-5% |
-5% |
-10% |
+55% |
これらの運用は、両方とも5年間の平均利回り5%となります。しかし、100万円を元本として運用した場合以下のような結果になります。
|
|
|
1年目 |
2年目 |
3年目 |
4年目 |
5年目 |
|
運用① |
利回り |
+5% |
+5% |
+5% |
+5% |
+5% |
|
運用結果 |
105万円 |
110.25万円 |
115.76万円 |
121.55万円 |
127.63万円 |
|
|
運用② |
利回り |
-10% |
-5% |
-5% |
-10% |
+55% |
|
運用結果 |
90万円 |
85.5万円 |
81.23万円 |
73.10万円 |
113.31万円 |
平均利回りが同じなのに運用結果が大きく異なります。これは、一度元本が減ってしまうと、元の金額まで戻すにはそれ以上の運用成果が必要なためです。例えば、100万円が10%減って90万円になってしまった場合に、そこから同じように10%増やしたとしても99万円にしかならず、100万円に戻すには1.1%の利回りが必要になります。
これらから、算術平均での平均利回りは単純に信頼するのは避けたほうが良いということがわかります。
幾何平均
幾何平均
続いてもう一つの平均利回りである幾何平均利回りについてみていきましょう。
幾何平均利回りは運用年数をn 年とした場合に各年の利回りの伸び率(前年度に対して何割になったか)を掛け合わせたものn乗根で求めることができます。
n√(100%+1年目の利回り)×(100%+2年目の利回り)×…(100%+n年目の利回り)-100%
幾何平均利回りで先ほどの運用①と運用②の利回りを計算すると以下のようになります。
運用①:5√{(100+5)×(100+5)×(100+5)×(100+5)×(100+5)}-100%=5%
運用②:5√{(100-10)×(100-5)×(100-5)×(100-10)×(100+55)}-100%=3%
このように幾何平均で計算すると、算術平均とは異なり平均利回りに変化が生じます。この理由は、幾何平均は毎年の資産の成長の伸び率を平均したものなので、算術平均に比べると実際の運用成果に近い数値を算出することができます。
これらの結果から、過去の結果から平均利回りを計算するには幾何平均を使用するべきだということがわかります。
まとめ
投資信託を選択するには様々な指標を参考にする必要がありますが、その中でも平均利回りは運用成果に直結する大切な指標です。ただし、投資信託はあくまでもリスク資産のためその平均利回り通りに運用成果が出るとは限りません。詳しく分析するにはその平均利回りの計算方法がどのような手法を用いているのかにも注意してみていくようにしましょう。